暴落の概要
「暴落」とは、株式市場が急激に下落する現象を指します。
通常、株価は長期的には上昇傾向にありますが、短期的には大きな値動きがあり、その中には突然の急落が含まれることもあります。
暴落が発生すると、投資家の心理が一気に冷え込み、多くの人がパニック売りを始めることになります。
その結果、市場全体の資産価値が大幅に下がり、特にリタイアメントを目指すFIREの人々にとっては非常に大きなリスクとなります。
暴落が必ず起こる理由
暴落は必然的に発生する現象であり、経済の成長、インフレ、金利、雇用などの要素が絡み合って引き起こされます。
経済が成長するとインフレが進行し、それに対応するためにFRBは金利を引き上げます。
金利が上がることで経済活動が鈍化し、雇用不安定や企業の収益減少が進行します。
その結果、株式市場が暴落することとなり、暴落は避けられない現象として繰り返されます。
1. 経済成長とインフレ
経済が成長すると、企業は収益を増加させ、消費者の購買意欲も高まります。
これにより、物価が上昇し、インフレが進行します。適度なインフレは経済の健全な成長を示しますが、過剰なインフレは問題を引き起こします。
- インフレの進行: 経済が成長すると、需要が供給を上回り、商品やサービスの価格が上昇します。これがインフレの一因となります。
- インフレの影響: 過剰なインフレは、消費者の購買力を低下させ、企業のコストも増加させます。結果として、企業の利益率が圧迫され、経済のバランスが崩れます。
2. FRB(アメリカ連邦準備制度)による金利引き上げ
インフレが進行すると、FRBなどの中央銀行は経済を冷やすために金利を引き上げます。
金利を上げることで、借り入れコストが増加し、消費者や企業の支出が減少します。
これにより、インフレを抑制し、経済の過熱を防ぎます。
- 金利引き上げの目的: 金利を上げることで、借り入れコストが高くなり、企業や消費者の過剰な投資や消費が抑制されます。これがインフレの抑制に繋がります。
- 金利の影響: 高金利は、住宅ローンや企業の設備投資、消費者の消費支出などに直接的な影響を与え、経済活動が鈍化します。
3. 金利上昇による経済鈍化と雇用不安定
金利の引き上げは、経済全体の活動を鈍化させます。
特に、借り入れコストが増加するため、企業の投資活動が減少し、消費者も高いローン金利を避けるようになります。
これにより、経済の成長が停滞し、雇用情勢にも悪影響が出ます。
- 企業の投資減少: 高金利は、企業が設備投資や事業拡大を行う際のコストを増加させるため、投資を控えることになります。これが経済の成長を鈍化させます。
- 雇用不安定化: 経済が鈍化すると、企業の収益が減少し、人員削減や労働条件の悪化が起こる可能性があります。これにより、雇用が不安定になり、消費者の信頼感も低下します。
4. 経済悪化と株価暴落
経済の鈍化と雇用の不安定化が続くと、市場の投資家の信頼感も低下し、株式市場が売りに転じます。
企業の利益が減少し、株価が下落することで、さらに経済が悪化し、暴落が発生します。
- 投資家の不安: 金利上昇による経済の鈍化や雇用不安定が長期化すると、投資家は企業の利益成長が見込めないと判断し、株式を売却します。この売り圧力が株価を下げ、暴落を引き起こします。
- 暴落の連鎖: 株価の下落は、企業の財務状況や消費者心理に悪影響を与え、さらに景気後退を加速させます。暴落は、経済の低迷と相まって、さらなる投資家不安を引き起こし、悪循環に陥ります。
これまでに発生した暴落の事例
- 1970年代のスタグフレーション
- 原因: 石油危機によるインフレの急上昇と、金利の引き上げが背景にあります。高インフレと経済成長の鈍化が同時に進行し、株式市場は大きな打撃を受けました。
- 原因: 石油危機によるインフレの急上昇と、金利の引き上げが背景にあります。高インフレと経済成長の鈍化が同時に進行し、株式市場は大きな打撃を受けました。
- 2008年のリーマンショック
- 原因: サブプライムローン危機による金融機関の破綻と、金利引き上げが背景にあります。FRBが金利を引き上げ、過剰な信用膨張が崩壊し、世界的な株式市場の暴落を引き起こしました。
- 原因: サブプライムローン危機による金融機関の破綻と、金利引き上げが背景にあります。FRBが金利を引き上げ、過剰な信用膨張が崩壊し、世界的な株式市場の暴落を引き起こしました。
- 2020年のCOVID-19パンデミック
- 原因: パンデミックによる経済活動の停止と、それに伴う企業の収益減少。加えて、金利政策や雇用市場の不安定化が株価を暴落させました。
- 原因: パンデミックによる経済活動の停止と、それに伴う企業の収益減少。加えて、金利政策や雇用市場の不安定化が株価を暴落させました。
暴落対策の基本戦略
1. 現金クッション
暴落に備えるための最も基本的な対策は、現金クッションを用意することです。
現金クッションとは、生活費や予備費を現金として保有しておくことを意味します。
特に、リタイア後の数年分の生活費を現金で準備しておくことが推奨されます。
これにより、暴落が発生した際でも、急いで資産を売却して生活資金を確保する必要がなくなります。
現金クッションは、相場が低迷している間も、安定した生活を維持するために非常に重要な役割を果たします。
暴落が続いている間、株やその他のリスク資産を売却せずに済むため、資産が回復するのを待つことができます。
例えば、FIREの第一人者の一人「クリスティー・シェン」氏は過去の市場暴落が通常2~5年で回復していることを調査し、5年分の生活費を現金として保持することで、暴落期間中に資産を売却せずに生活できると提案しています。
2. 債券、ゴールド
暴落対策のもう一つの有効な手段は、債券やゴールドなどの比較的安定した資産を保有することです。
- 債券は、株式に比べて価格の変動が少なく、安定しているため、株式市場の暴落時に避難先として活用されます。特に、国債などの信用度の高い債券は、価格の変動が少ないため、安全資産として位置付けられます。
- ゴールドもまた、資産を保護するための安全資産として長い歴史があります。ゴールドは、通貨の価値が下がる時や市場が不安定な時に価値を保つことが多いため、資産の分散投資として有効です。
これらの資産は、暴落時に株式の下落をカバーし、全体のポートフォリオのリスクを減らすことができます。
※ポートフォリオの基本的な解説はこちら
👉️ポートフォリオ|FIRE民は“分散ポートフォリオ”の理解が必須
※暴落対策として現金や債券、ゴールドを取り入れたポートフォリオの評価方法はこちらで解説
👉️ポートフォリオ|そのポートフォリオ、本当に大丈夫? – 評価方法を学んで、FIREの不安を数字で解消しよう
※暴落対策として現金、債券、ゴールドを取り入れた筆者のポートフォリオの解説はこちら
👉️オールシーズンズ戦略|FIREした筆者が実践している安心のポートフォリオ(概要解説)
3. 労働
リタイア後にすべての収入源を資産運用に依存するのではなく、労働という選択肢も考慮に入れるべきです。
副収入として働くことで、資産の取り崩しを避け、生活費を賄うことができます。
また、収入源が一つではなく複数あると、万が一暴落が発生しても、生活基盤が揺らぎにくくなります。
もちろん、完全なFIRE(Financial Independence, Retire Early)を目指す場合、労働を極力避けることが理想かもしれません。
しかし、暴落リスクを最小限に抑えるために、柔軟に考えることが大切です。
特に、フリーランスや自営業として働くことができれば、生活費を十分に補いながら、精神的にも安定した生活を送ることができます
結論
暴落対策は、FIREを実現した後の生活を守るために非常に重要です。
暴落やシーケンスリスクを恐れることなく、安定した生活を送り続けるためには、現金クッションを準備したり、安定した資産(債券やゴールド)に分散投資したり、労働による副収入を得ることが大切です。
これらの対策をしっかりと講じておけば、どんな市場の変動にも対応できるでしょう。


 オールシーズンズ戦略|FIREした筆者が実践している安心のポートフォリオ(概要解説)
オールシーズンズ戦略|FIREした筆者が実践している安心のポートフォリオ(概要解説) FIREとは? ー自立と自由を手に入れるFIREの全貌ー
FIREとは? ー自立と自由を手に入れるFIREの全貌ー サイドFIRE|もっと早く知っておくべきだった。実践者が語る必要資産と働き方
サイドFIRE|もっと早く知っておくべきだった。実践者が語る必要資産と働き方 オールシーズンズ戦略|FIREした筆者が実践している安心のポートフォリオ(詳細解説)
オールシーズンズ戦略|FIREした筆者が実践している安心のポートフォリオ(詳細解説)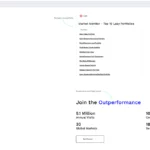 ポートフォリオ|【超簡単に】Portfolio Visualizerの使い方
ポートフォリオ|【超簡単に】Portfolio Visualizerの使い方 オールシーズンズ戦略|実践者が基本を解説。暴落でも安心!その魅力とは?
オールシーズンズ戦略|実践者が基本を解説。暴落でも安心!その魅力とは?